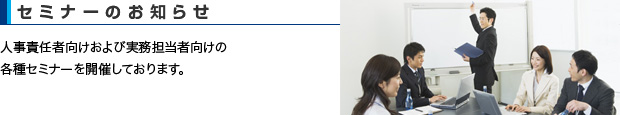| ■福岡経協セミナー |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| ■無料オンデマンド配信サービス |
 |
 |
 |
 |
| |
●「LGBTqと労務管理」講座 (2022.02.07更新) |
|
 |
最近頻繁に話題となっているLGBTqについて、その概念や労務管理にまつわる法制度、労務管理関連の裁判例などを、会社側の立場から解説します。
<内容>
・ダイバーシティと企業価値
・LGBTqの概念
・LGBTqと労務管理にまつわる法制度
・LGBTqに関する労務管理関連の裁判例
・企業の取り組み
・ジェンダーハラスメントの意識向上
・パワーハラスメントの意識の向上
お申込みはこちらへ。
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| |
●「元労働基準監督官が語る労基法・安衛法送検事例研究」講座 (2021.07.08更新) |
|
 |
元労働基準監督官による労働基準監督官の捜査内容、労基法・安衛法違反での送検事例について解説します。
<内容>
・労働基準監督官の捜査について
・捜査の現状について
・ブラック企業と呼ばれてしまう労基法違反
(長時間労働による送検、繰り返し違反による送検、
過労死事案、虚偽報告事案)
・送検されないために
(労働時間の把握義務、
労務管理リスク削減長時間労働の削減、
労災事故の防止等)
お申込みはこちらへ。
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| |
●ジョブ型雇用導入における法的留意点 (2021.04.05更新) |
|
 |
ジョブ型雇用の概要や導入における法的留意点等について、会社側の立場から解説します。
<内容>
ジョブ型雇用
第1 ジョブ型雇用の概要
第2 職務記述書(JD)の作成
第3 ジョブ型雇用導入における法的留意点
お申込みはこちらへ。
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| |
●パワハラ防止のための判断基準、人事管理、相談対応 (2021.03.01更新) |
|
 |
パワーハラスメントの判断基準や具体例、その防止措置、要因そのものへの対処等について、会社側の立場から解説します。
<内容>
パワハラ防止のための
第一章 なぜパワハラを防止しなければならないか?
第二章 パワーハラスメントの判断基準と具体例
第三章 防止措置と何を講じるべきか
第四章 パワハラの要因そのものへの対処
第五章 相談対応における悩みどころ
第六章 カスタマーハラスメント
お申込みはこちらへ。
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |